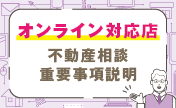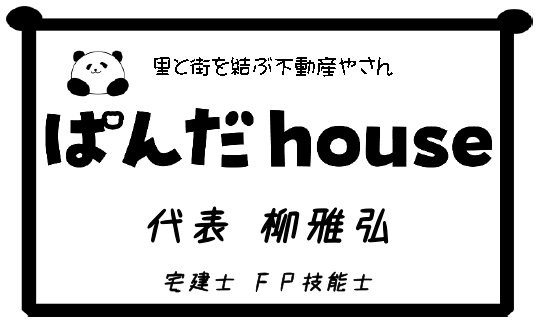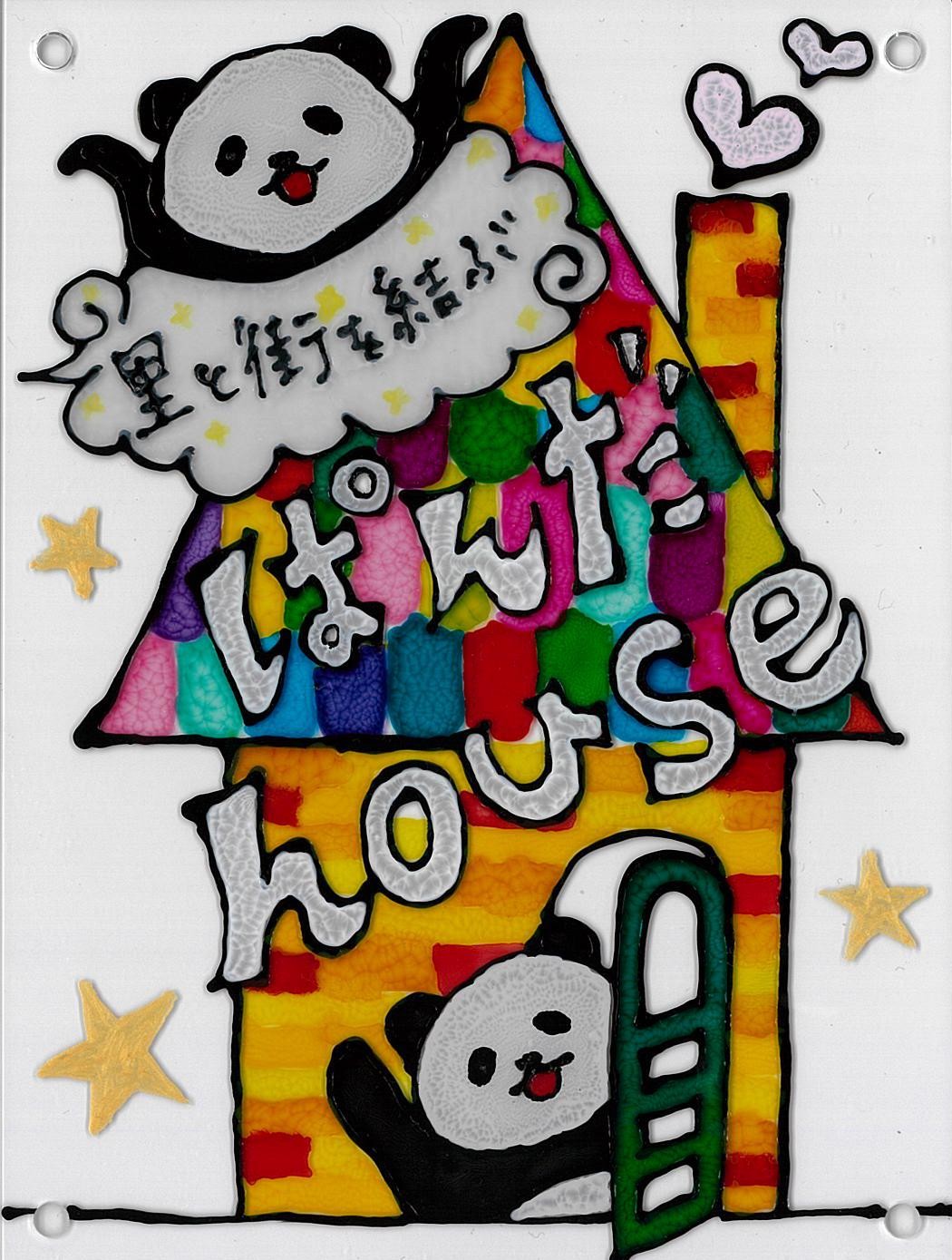消滅時効とは?
ざっくり言うと、 「長い間行使されなかった権利が、一定期間経つと消えてしまう制度」 です。 債権(お金を返してもらう権利)でよく問題になる 民法166条以下に規定
イメージ AさんがBさんに100万円貸した でもBさんから返済請求が10年間まったくない この場合、法律上「請求できる権利が消滅する」 👉 これが消滅時効 💡 「使わない権利は法律上消える」というイメージ
期間の目安(民法改正後) 原則債権:5年(2020年4月1日以降) 売買代金や請負代金など日常的な取引:5年 一定の特殊債権:10年や20年などケース別 ※旧民法では原則10年だった
ポイント 時効の開始 債権者が権利を行使できることを知った時点、または権利が発生した時点からスタート 援用が必要 時効は自動的に消えるわけではなく、「消滅時効を主張します」と言うこと(援用)で成立 時効の更新・中断 一度請求したり、裁判を起こすと時効が止まる 「債務者が一部返済した」「承認した」なども中断要件
実務での注意点 不動産賃貸料やローンの請求権も時効で消える場合がある 証拠を残しておかないと、時効援用の争いで不利になる 「5年経ったらOK」と思わず、きちんと権利管理することが重要
ポイントまとめ 消滅時効=「長期間使わない権利は消える制度」 原則5年(旧法では10年) 時効の援用が必要、更新・中断も可能
ゆるいまとめ 消滅時効は、 「放置された権利は法律がリセットしてくれる」制度。 ただし、 使っていないからといって自動で消えるわけではない 請求や確認を怠らず、必要なら援用することがポイントです