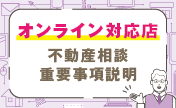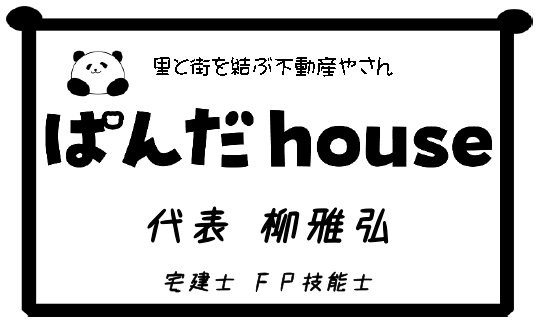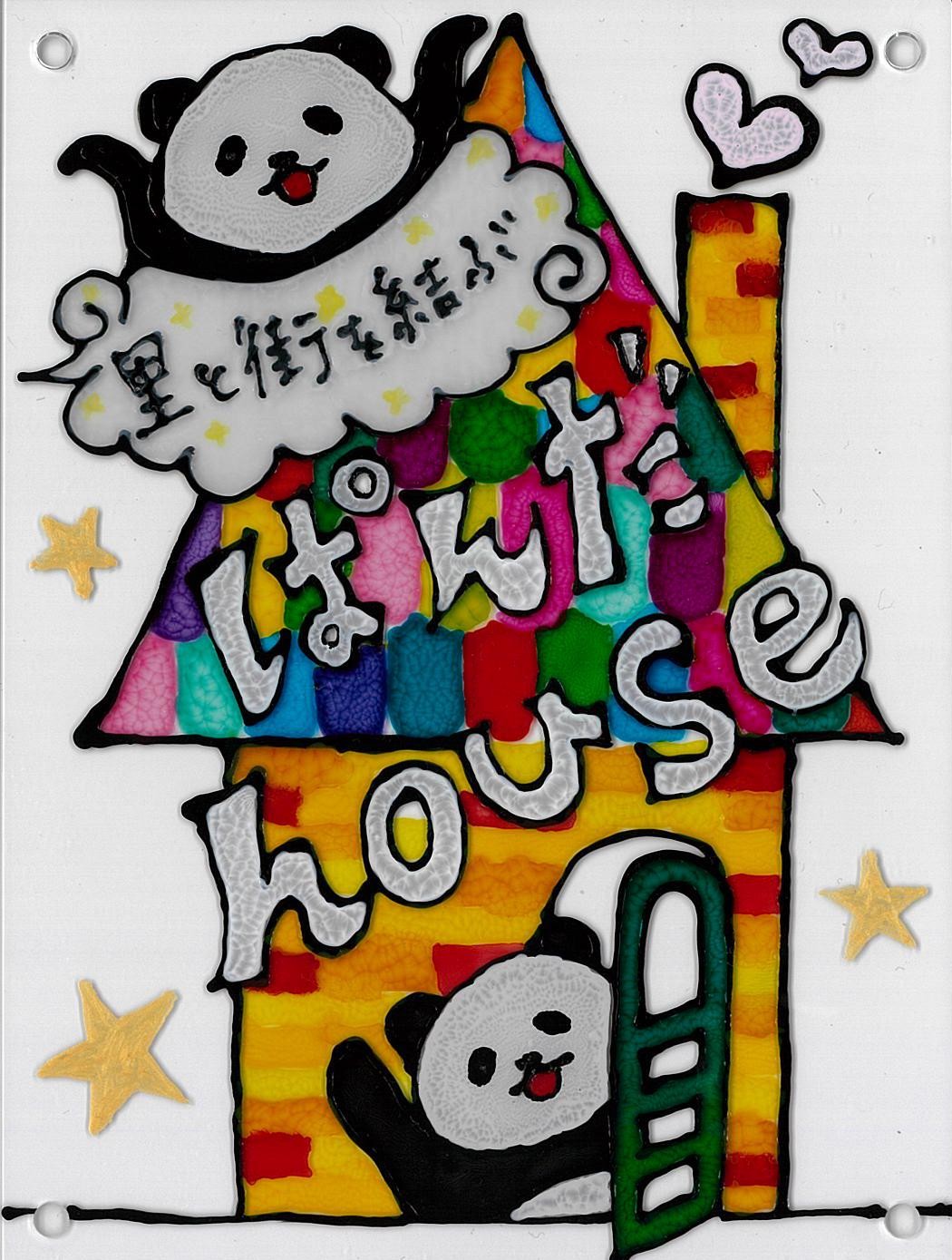宅建士ってなに? 〜不動産取引の“守護神”的な存在〜
不動産会社に行くと、たまに胸元に「宅地建物取引士証」を下げた人を見かけませんか? これが、いわゆる 宅建士(宅地建物取引士)。 「国家資格を持っている人」ということはなんとなく知っていても、 実際にどんな役割を果たしているのかは意外と知られていません。
宅建士制度の役割 不動産取引は高額で、しかも専門知識が必要。 だから、ただの営業トークだけでは安心できませんよね。 そこで登場するのが宅建士。 法律上、宅建士には大きく3つの役割があります。
重要事項説明を買主や借主に直接説明する
重要事項説明書や契約書に署名・押印する
事務所ごとに一定数の宅建士を設置する
つまり、宅建士がいることで「法律に基づいた説明が必ず行われる」仕組みになっているんです。
注意点 ここでの注意点は、「宅建士が説明する=100%安心」ではないということ。 宅建士の知識や経験にも差がある 説明が形式的になってしまうケースもある
実際に質問すると「営業担当に聞いてください」となることも なので、宅建士が出てきたら「聞いていいのかな?」と遠慮せず、 納得いくまで質問するのが大事です。
説明のポイント 消費者目線で押さえておきたいのは、
重要事項説明は宅建士しかできない(営業担当だけではNG)
宅建士証を提示して説明する義務がある
契約書や重要事項説明書に宅建士の署名・押印が入っていないと無効
このあたりを知っておくと、説明を受けるときに「ちゃんと制度通りにやってるな」と安心できます。
一般消費者への影響
売主さん:契約相手にトラブルが起きにくく、取引の信頼性が増す
買主さん・借主さん:プロの資格者から説明を受けることで、リスクを理解したうえで契約できる
つまり宅建士制度は、取引の透明性を高めて、消費者を守るための「最低ライン」を確保する仕組みなんです。
まとめ
宅建士は、不動産取引の世界でいわば“守護神”的な存在。 実際の契約の場面では「宅建士が出てきて、しっかり説明してくれたか?」をひとつの安心材料にしてみてください。 大事なお金が動く場面だからこそ、制度を知っておくことで、不安をグッと減らすことができますよ。