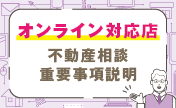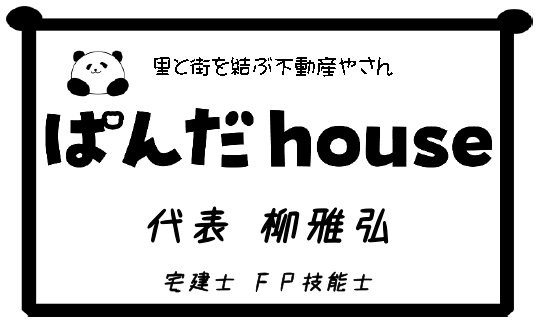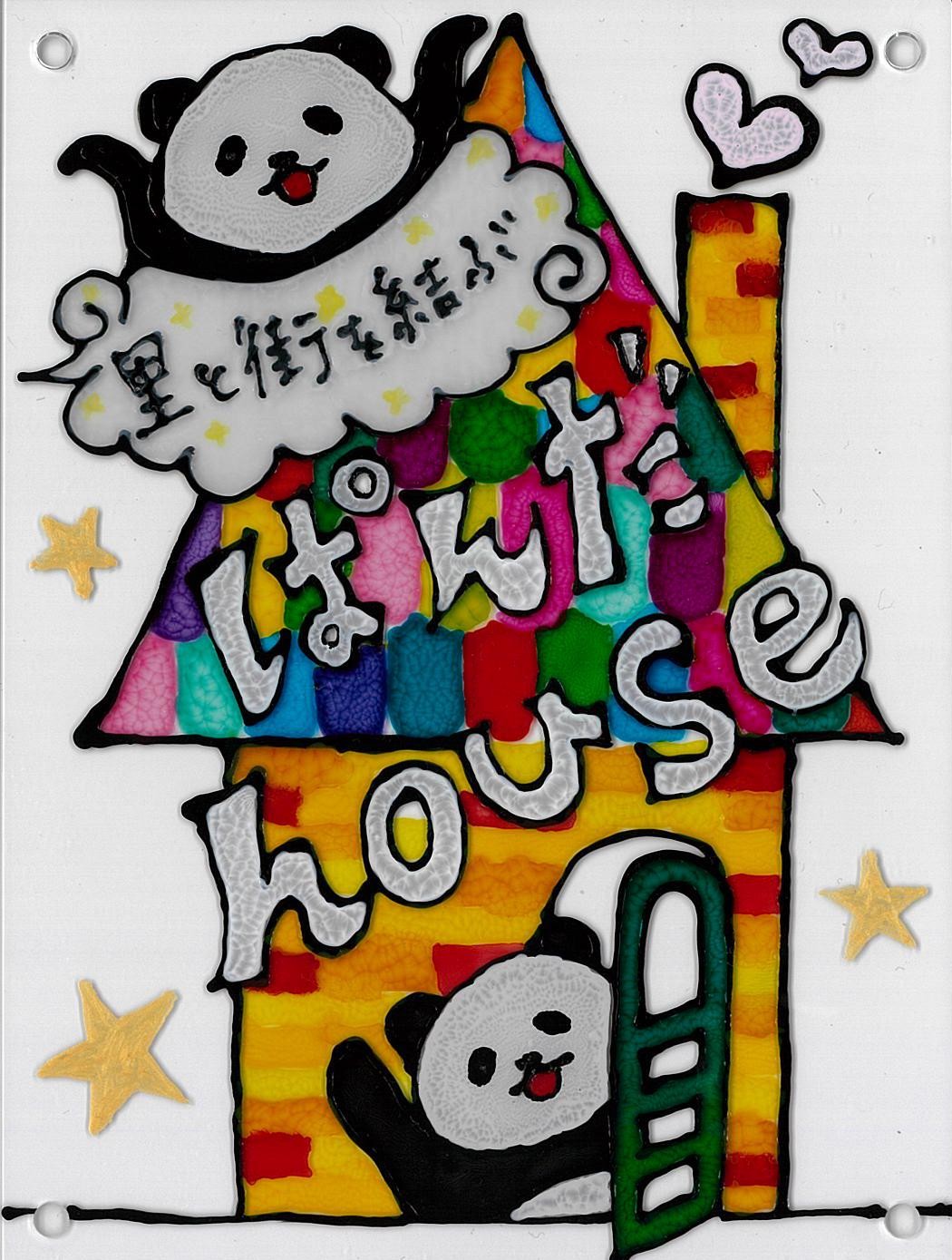不動産取引と民法改正。
知っておきたいポイント 2020年4月に施行された民法改正。 「120年ぶりの大改正!」なんてニュースになったので耳にした方も多いと思います。 でも実際、私たちが不動産を売ったり買ったりするときに、どんな影響があるのでしょうか? 今日はその“重要なポイント”を、やわらかくかみ砕いてご紹介します。
① 瑕疵担保責任から「契約不適合責任」へ これまでは、買った不動産に“隠れた欠陥(瑕疵)”があった場合に売主が責任を負う「瑕疵担保責任」という制度でした。 改正後は「契約不適合責任」に名前も中身も変わりました。 要は… 契約で約束した内容に合っていなければ責任を問える 買主は修補請求や代金減額請求もできる と、買主の権利が広がったわけです。
売主にとっては「説明責任が重くなった」といえるので、不動産業者と一緒に丁寧に告知書を書くのが大切になります。
② 買主の請求権が増えた 従来は「損害賠償か契約解除」くらいしか選択肢がなかったのですが、改正後は 修補請求(直して!) 代金減額請求(値引いて!) 損害賠償請求(損した分払って!) 契約解除(もう白紙にして!) と、買主側の選択肢が充実しました。
買主にとっては安心感アップ。売主にとってはリスク管理がより大切に。
③ 消滅時効のルールがシンプルに 「10年」とか「20年」とか複雑だった時効が、「5年 or 10年」に整理されました。 つまり、不動産トラブルが長引いて“いつまで責任を問えるのか”が、以前よりわかりやすくなったのです。
④ 個人保証の制限もポイント 不動産取引に関係する場面としては、借入時の「保証人」の取り扱いも厳格になりました。 特に事業用不動産を購入する方にとっては、「安易に連帯保証人を立てられない」点が安心材料になります。
まとめ 民法改正によって、不動産取引は「買主の権利が強化された」といえます。 そのぶん売主や業者は、これまで以上に説明や契約内容をしっかり詰める必要がある。 でも、裏を返せば「トラブルを防ぐ仕組みが整った」ということでもあります。
ポイントは、「契約はきっちり。でも説明はわかりやすく」。 せっかくの不動産取引ですから、お互いに気持ちよく進められるよう、この改正を“安心材料”として活用したいですね。