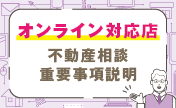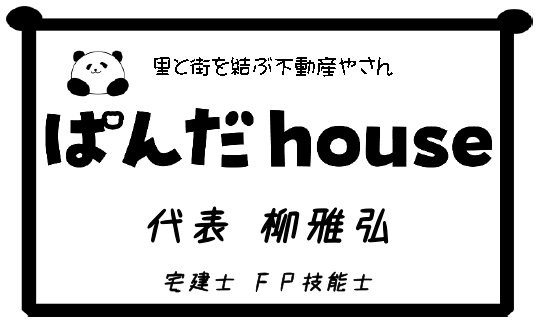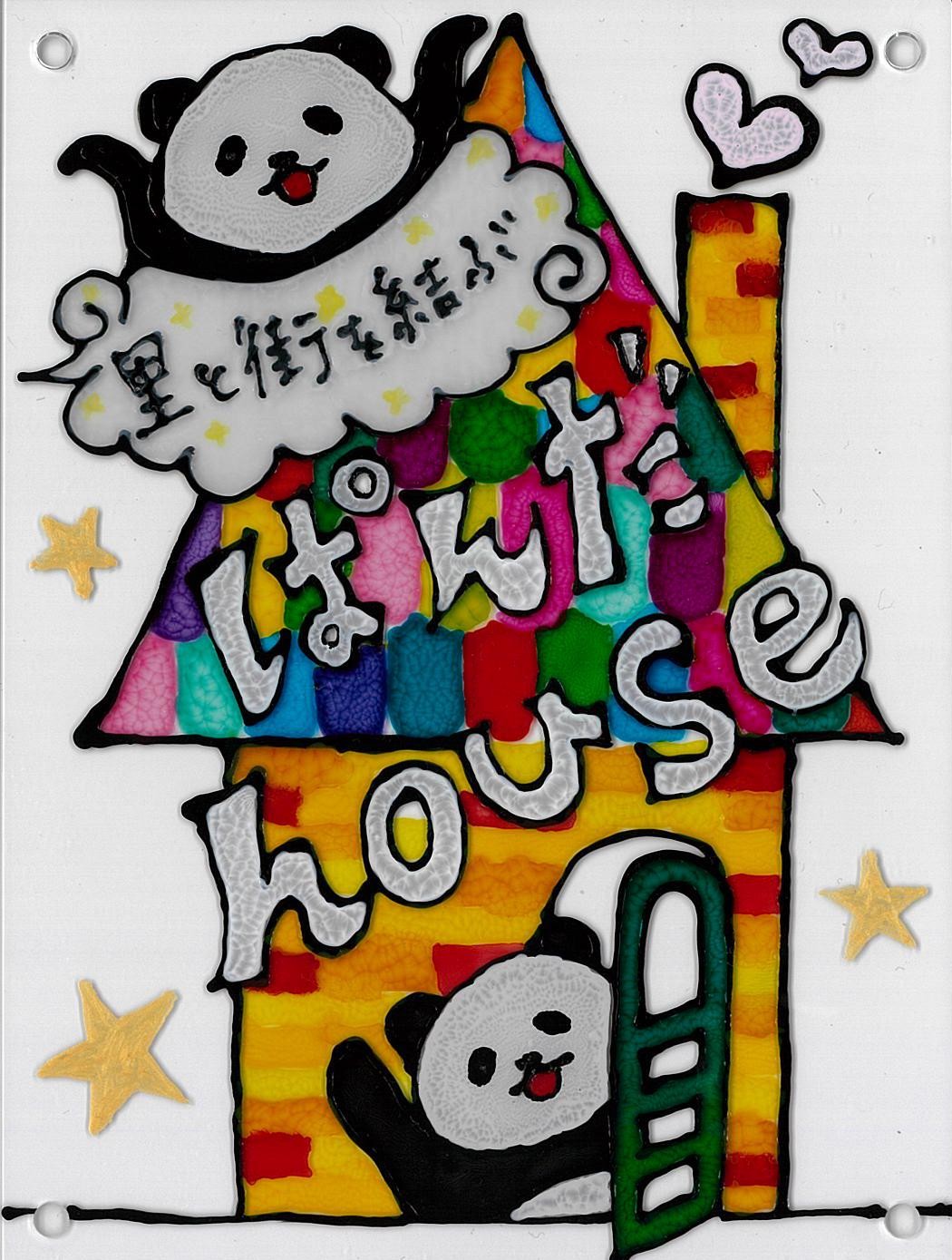不動産売買と「担保責任」ってなに?
家を売ったり買ったりする時に、「ちゃんと引き渡せばOK!」と思ってしまいがちですが、実はそれだけでは済まない場合があります。 それが 「担保責任」 というルールです。
担保責任の基本イメージ たとえば中古住宅を買ったあとに… 雨漏りが発覚した! シロアリ被害が広がっていた! 実は他人の権利がついていて自由に使えない! こんなトラブルがあったら、買主としては「ちょっと待ってよ!」となりますよね。 そこで売主に一定の責任を負わせるのが「担保責任」です。 法律的には「契約不適合責任」という呼び方に変わりましたが、意味は近いので実務ではまだ「担保責任」と言う人も多いです。
どんなときに発生するの? 担保責任(契約不適合責任)が問われるのは、 「契約で約束した内容と違うモノを渡した場合」 です。 具体的には… 土地の一部が他人のものだった(境界トラブル) 建物に重大な欠陥があった(雨漏り・基礎のひび割れなど) 登記がちゃんと移転できなかった など。 売主に「わざと隠した」かどうかは関係なく、結果的に契約と違うものを渡していたら責任を負うことになります。
買主ができること もし担保責任が発生した場合、買主にはいくつかの選択肢があります。 修補請求(直してください) 代金減額請求(値引きしてください) 契約解除(もう買いません) 損害賠償請求(修理代など負担してください) 状況に応じて、買主はこれらを選べる仕組みになっています。
売主が注意すべきポイント 売主にとっては、「そんなの知らなかった…」でも責任を負うケースがあるので注意が必要です。 引き渡す前に建物調査(インスペクション)を受ける 契約書に免責事項を明確に書いてもらう(個人間売買では「現状有姿・瑕疵担保免責」とすることも多い) 境界や権利関係は必ず確認(測量図・登記簿・隣地との同意) ちょっとの手間で、大きなトラブルを未然に防げます。
まとめ 担保責任(契約不適合責任)は、 「売った後に“知らなかった欠陥”が見つかっても責任を問われる可能性がある」ルール。 売主は「引き渡せば終わり!」ではなく、 「後から揉めない準備」まで考えておくことが安心につながります。