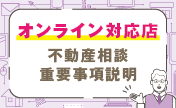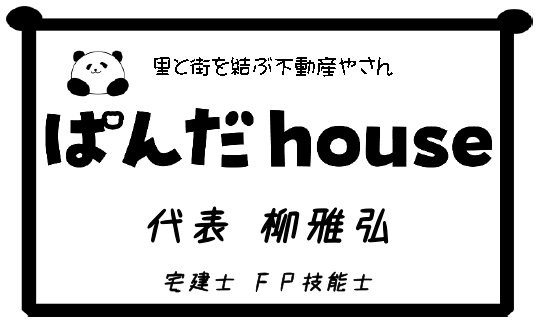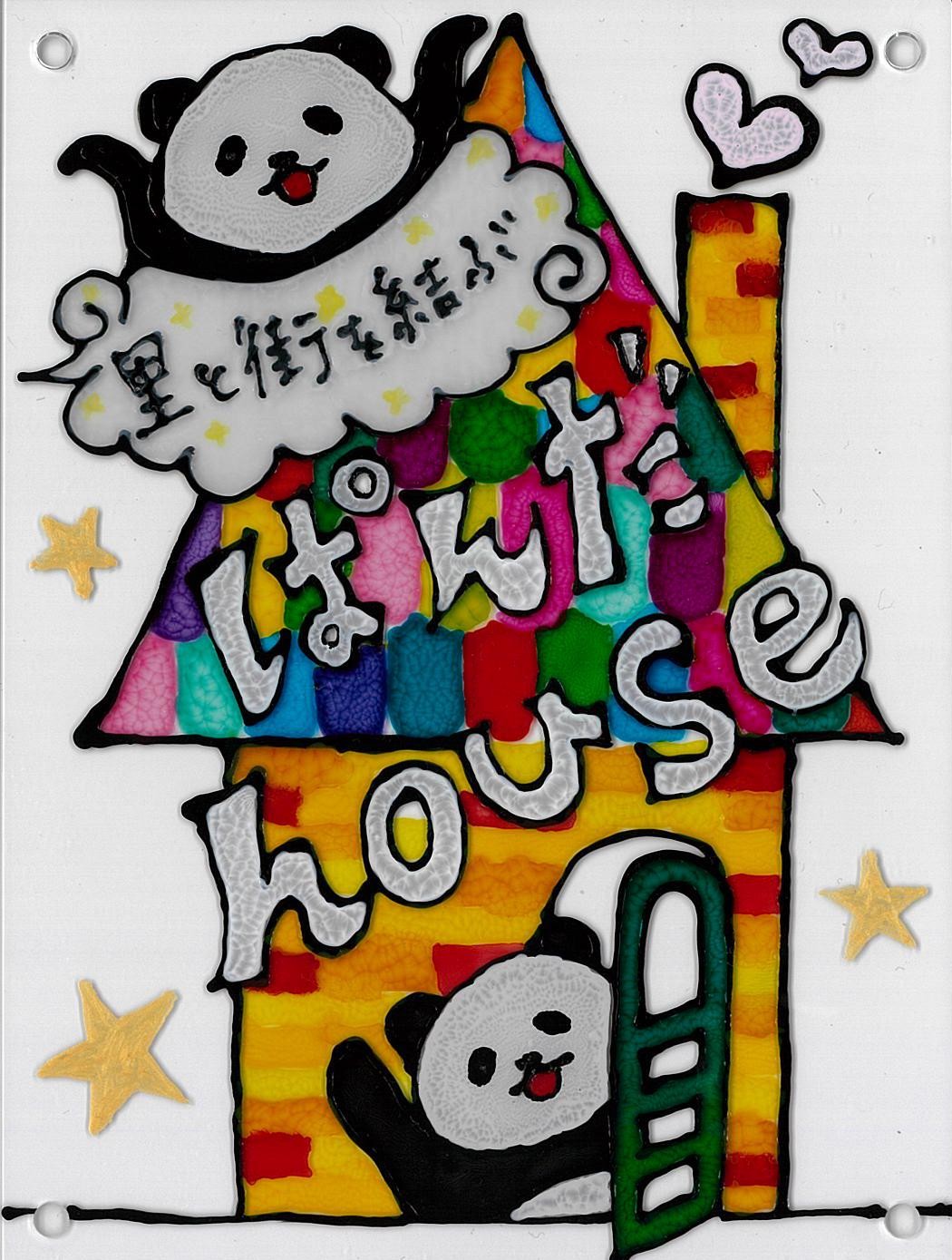「相続した空き家どうする?売却・管理・活用方法をケース別に解説」
空き家問題をめぐる物語 ―親の家をどうするか、あなたが直面するかもしれない未来―
1. 物語のはじまり ― ある相続の場面から 60代の健一さんは、父の死去をきっかけに、地方に残された実家を相続しました。 東京で長年暮らす健一さんにとって、その家は幼少期の思い出の場所。しかし、築50年の木造住宅は老朽化が進み、修繕費もかかる。使う予定も貸す予定もなく、放置して数年。気づけば庭は雑草に覆われ、近隣から「害虫が出ている」「不審者が入っているかもしれない」と苦情が来るようになりました。 健一さんは、ようやく「空き家問題」と向き合わざるを得なくなったのです。
2. 空き家問題の原因 空き家が増える背景には、複数の要因が絡み合っています。 人口減少と少子高齢化 都市部に人口が集中し、地方や郊外の住宅は使い手が減少。相続しても「使わない」家が増える。
相続のタイミング 親が亡くなった後、実家をどうするかの結論を出せないまま放置 → 結果的に空き家化。
住宅の過剰供給 日本は欧米に比べ中古住宅の流通が弱く、新築志向が強い。古い家は「資産」ではなく「負担」と見なされやすい。
権利関係の複雑さ 相続人が多い場合、誰も単独で意思決定できず、話がまとまらない。
3. 空き家がもたらす課題 放置された空き家は、個人の問題にとどまらず、地域社会にも悪影響を及ぼします。
治安・衛生問題:不法投棄、不審者の侵入、害虫や雑草の繁殖
景観・不動産価値の低下:近隣地の資産価値にも影響
防災リスク:老朽化による倒壊、火災の危険性
相続人の負担:固定資産税・管理費用・近隣トラブル対応
4. 行政や事業者の取り組み この社会的課題に対して、国や自治体、民間事業者も動き始めています。
行政の取り組み
空家等対策特別措置法(2015年施行、2023年改正) 管理不全空き家に対して指導・勧告・行政代執行が可能に。固定資産税の優遇措置解除もあり。
補助金制度 解体費用の一部助成、リフォーム支援金、空き家バンク登録への助成など。
空き家バンク 自治体が空き家所有者と移住希望者・事業者をつなぐ仕組み。
民間事業者の取り組み 不動産会社の「空き家管理サービス」:定期巡回、草刈り、通風、清掃など
リノベーション・コンバージョン:古民家カフェ、シェアハウス、観光拠点への転用
買取・再販モデル:専門業者が空き家を買い取り、リフォーム後に再販売
5. 相続人が準備すべきこと いざ相続が発生してから慌てるのでは遅い。事前の準備が肝心です。 相続発生前に親と話し合う
・「実家を将来どうするか」を共有しておくことが一番重要。
・売却か、賃貸か、子や孫が住むのか。 権利関係を整理する
・登記簿を確認し、相続登記を放置しない(2024年から相続登記は義務化)。
・共有者が多い場合は早めに分割協議。 選択肢をシミュレーションする
・売却 → 早期に処分し資産化
・賃貸 → リフォームして収益化
・管理 → 自治体や業者に委託 固定資産税・維持費を把握する
・「空き家特例」が解除されれば税負担は最大6倍になるリスクあり。 補助金・制度を調べておく
・自治体ごとの解体補助、改修補助を活用すれば大きな負担減。
6. 物語の結末 ― 健一さんの選択 健一さんは、弁護士・不動産業者・市役所に相談。 結果として「実家を売却し、空き家バンクを通じて移住者に引き継ぐ」道を選びました。 売却益は相続人で公平に分け、地域には新しい住人が加わる。 放置すれば負担だった家が、次の世代に「価値」としてバトンタッチされたのです。
まとめ 空き家問題は「遠い社会問題」ではなく、誰もが直面し得る 身近な相続の現実。 原因は人口構造や相続の複雑さにあり、課題は治安・財産・地域価値に及びます。 行政・事業者も動き出していますが、最も重要なのは 所有者・相続人の早めの準備と意思決定。 つまり、空き家問題を「地域の負担」にするか「新しい価値」にするかは、相続人の選択次第なのです。