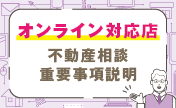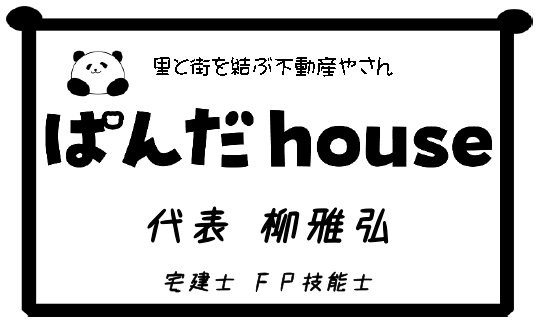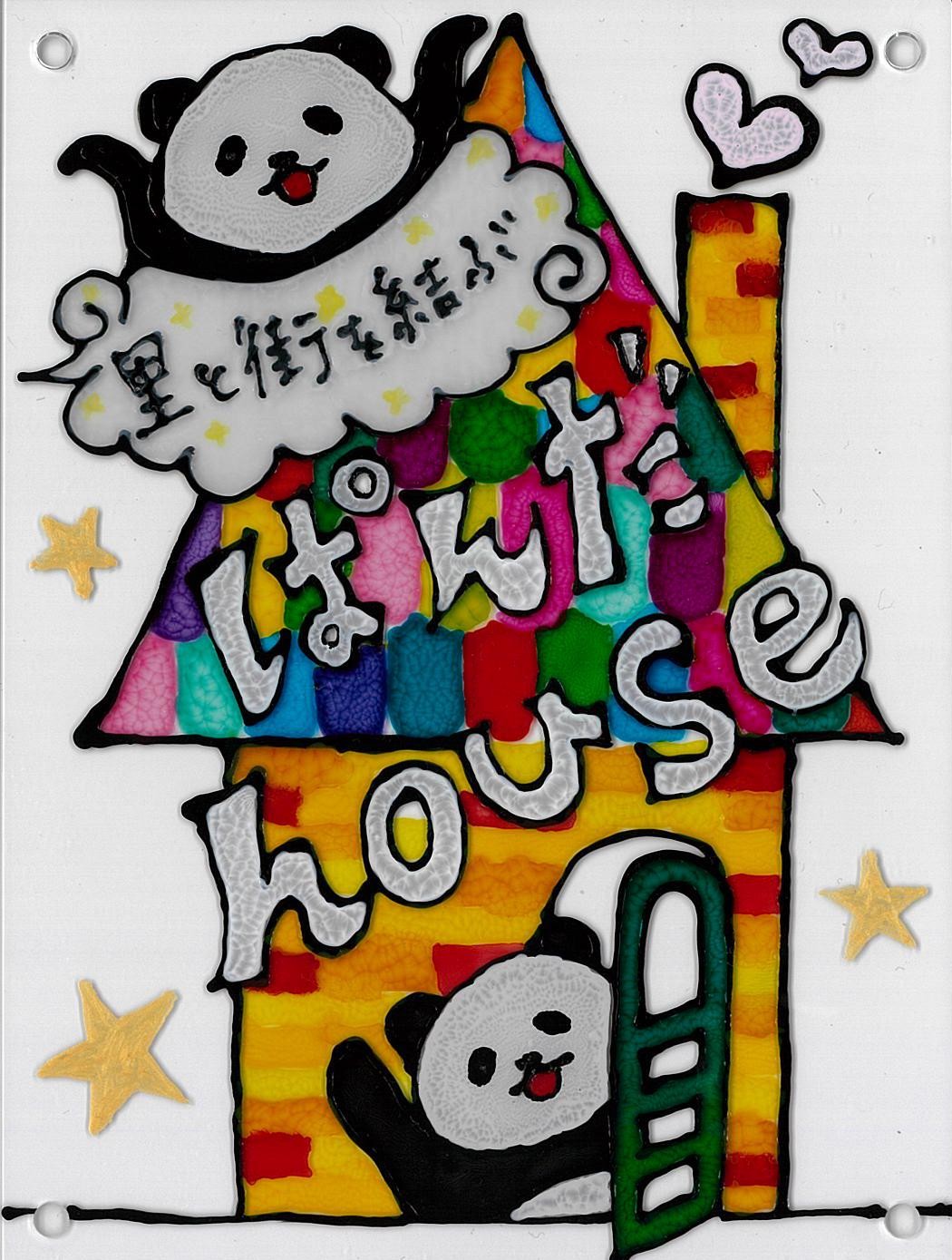空き家を放置すると税金が上がる?特定空き家に指定されるリスクや罰則、管理義務などを詳しく説明します。
正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。
1. 概要 被相続人(亡くなった方)が一人暮らしで住んでいた家やその敷地を、 相続開始から3年目の年末までに売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度。 売却益が3,000万円以下なら譲渡所得税がゼロになる可能性あり。
2. 適用条件(主なポイント)
被相続人の居住状況 相続開始直前まで一人で住んでいた(配偶者や同居親族がいない)
建物の築年数 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(旧耐震基準)
建物の状態 相続時点で耐震基準不適合であること
売却時の対応 ①建物を解体して更地にして売る、または②耐震改修して売る
売却期限 相続開始の翌年1月1日から3年目の12月31日まで
売却相手 親族や特別な関係者(同族会社など)以外
過去利用制限 相続開始年の前年および前々年にこの特例や居住用財産の3,000万円控除を使っていない
3. 計算方法 課税譲渡所得 = 譲渡価格 −(取得費+譲渡費用)− 3,000万円(控除額) 控除後の所得が0以下になれば税額もゼロ。
4. 注意点 「空き家」期間の管理 放置で荒廃・倒壊の危険があると、自治体の特定空家認定で特例が使えなくなる可能性あり。
耐震基準の判定 建物を残して売る場合は耐震改修が必要(工事費用が発生)。
売却期限 「相続開始から3年目の年末」までが期限。売却契約がこの日を過ぎると適用不可。
書類の準備 被相続人の住民票除票、建物の登記事項証明書、解体証明書、契約書、耐震基準適合証明などが必要。
取得費不明の問題 古い物件で購入時資料がないと概算取得費(売却額の5%)になるため、控除前所得が多くなりやすい。
5. この制度のメリット
節税額が大きい(最大3,000万円×20%=最大約600万円の税金がゼロ)
長期譲渡所得の税率(20%)より軽減税率よりも効果が大きい
6. この制度のデメリット・注意
期限が短く計画的な売却が必要 耐震改修や解体費用が発生する 親族間売買は対象外
書類不備で否認されるケースがある(特に「一人で住んでいた証明」が抜けやすい)
この特例を確実に使うには、
登記事項証明書
被相続人の住民票除票
解体証明書(必要な場合)
売却契約書 などの準備が必要になります。
手続き流れ(推奨スケジュール)
相続発生〜3か月以内
登記(相続登記)完了
被相続人の住民票除票・戸籍除籍謄本取得
建物の登記事項証明書取得
相続発生〜6か月以内
建物の築年・耐震基準確認
解体 or 耐震改修の方向性決定
不動産会社選定・媒介契約
解体 or 改修着手
解体工事の場合:工事契約・解体証明書を確保
耐震改修の場合:耐震適合証明を取得
売却活動開始 期限まで約1年半前には販売開始
売却契約は期限の3か月前までに完了が安心
売却契約締結・決済 契約日は期限(12月31日)まで
決済は契約から1〜2か月後が一般的 翌年確定申告(2/16〜3/15)
特例適用書類一式を添付(住民票除票・除却証明・契約書など)